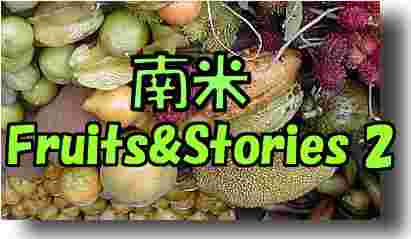
フェイジョア  2016年3月6日
2016年3月6日日本語名  フェイジョア フェイジョアブラジル  goiaba abacaxi goiaba abacaxiウルグアイ アルゼンチン 中国語 英語名  feijoa、pineapple guava feijoa、pineapple guava学名 別名  Orthostemon sellowiana O. Berg Orthostemon sellowiana O. Berg
グアバの仲間 日本名のアナナスガヤバは英語のパイナップルグアバあるいはブラジルのゴイアバアバカシの直訳ですが、フェイジョア という軽快な名前に比べるとさえない名前だと思います。 フェイジョアはブラジル南部のウルグアイやアルゼンチンと接する辺りからパラグアイが原産地で、山野に自生しているグアバの仲間です。 ブラジル南部のこのあたりの山地では雪が降るようなところもありますので寒さには結構強い果物です。 余り大きくならない木で根元からたくさん幹を出して藪になる低木です。  フェイジョアの花
フェイジョアの花花は大き目で直径6cm位でした。 外側は白く内側がきれいな赤色の厚めの花弁が4枚あります。長く飛び出した3cm位の多数の雄蕊が赤くて目立ちます。雌蕊も赤色です。 花が咲いてから時間がたつと赤色の花弁の横が上側に反り巻きこむので、花弁の裏側の白と赤い雄蕊が目立つ様になります。 花弁はちょっと甘く小鳥が花を食べに来て花粉を媒介をするとの説もあります。 近頃はサラダの色添えにして人も食べるようです。  売っていたブラジル産フェイジョア
売っていたブラジル産フェイジョア

果実は丸い卵型や細長い型をして膚面は滑らかですがボコボコしています。白っぽい緑色で頭に蕚片の残りが付いています。香りはグアバのすっきりした良い香りです。 緑の皮の下は白い硬めの果肉です。中側には軟らかくて透明感のある果肉に包まれて白くて小さい粒つぶの種子が入っています。 写真のものはブラジル南部のサンジョアキンと言うリンゴ産地の町へ行ったとき買ったものです。 長い形のものは長さ7、8cm太さ5cm位で重さは130g~140gでした。 丸い形のものは長さ6、7cm太さ6cm位で重さは120~130gでした。 種は白く2、3mmのインゲン豆の形で、あまり多くは入っていません。砂のような硬い種と硬くない種が混ざっていました。 縦に切ると外側の果肉は5-8mmの厚さで、硬くてざらざらし、甘くちょっと酸味もあり、渋味もありましたが、グアバの味でにおいはグアバよりも強かったです。切って放置すると断面は茶色になりました。中央のゼリー状のところの約60gは軟らかくグアバの香りをベースにパイナップルとバナナの甘い香りと味を楽しめました。種があってもあまり気になりません。 これは未熟の感じでしたが、追熟して果実の皮を剥かずに縦に切ってスプーンですくって食べるのがよさそうです。  熟して落ちたフェイジョア 熟して落ちたフェイジョア 
 日本で見たフェイジョアの果実は落ちていたもので、大きい方は長さ5cm、太さ3.2cm、重さは27gで、小さいのは重さ16gでした。この木には6月に花が咲いたのを見て、その後、実には気づかなかったのですが11月に緑色の果実を見つけました。12月には落ちていました。 軟らかくなった果実は強い香気があり、外側の果肉は甘味に渋味と酸味が加わりざらつき感がありましたが、種子の周りの果肉はゼリー状で熟した洋ナシの感じもあり甘くうまかったです。 名前の由来 学名は属名+種名+命名者名で出来ています 学名は参考にする本によって違うことがあります。フェイジョアの学名には最近のAPGの分類を採用した物ではAcca属が採用されています。 フェイジョア(feijoa)という属名はドイツの植物学者・薬剤師の ベルク(Otto Karl Berg )が付けたものです。 一番最初はAccaと言う属名を付けたのですが、 雄蕊がつき出ているとの意味で属名をOrthostemonに代えました。そのすぐ後、ブラジル生まれの博物学者フェイホ(João da Silva Feijó)にちなんでFeijoaにしました。Acca、Orthostemon、Feijoaもいずれも ベルクさんが付けた属名ということです。 後ろの種の部分はブラジルの植物を採集し研究したドイツ人のセロウ(Friedrich Sellow)に因んでいます。残念なことにセロウさんは42歳の若さで溺れて亡くなりました。 最新の名前はドイツの植物学者ブレット(Karl Ewald Maximilian Burret)さんが Feijoaを検証して1941年に、最初につけた属名Accaが適当であるとしました。KBには Accaの意味は分かりません。 この属名Accaは、最近使われだした遺伝子の解析を基にした分類体系(APG分類表)で採用されることになりました。 学名にはその植物の発見とか研究に由来する物語がよくあるのですが、分類学の発展により学名が変わると、こうしたエピソードは見えなくなり忘れられてしまいます。 果物としては新入り ブラジルの名前の意味は山のグアバやパイナップル味グアバで、ウルグアイ名は郷里のグアバといったところです。アルゼンチンで聞いた呼び名はグアバの偽物と言う意味です。原産地では山や原野に自然に生えているグアバの一つという認識です。 果物としての歴史は新しく1890年フランスの園芸家アンドレ(Edouard Andre)がウルグアイからヨーロッパに持って来て、地中海地方で良く育つことを1898年に園芸雑誌に書いたので、注目されて栽培されるようになりました。1900年にはカルフォルニアに導入されました。 ヨーロッパやアメリカ、ニュージーランドで幾つかの栽培品種が作られてアンドレ、チョイセアーナ、トライアンフ、マンモスなんて名前の栽培品種があります。KBはブラジルのリンゴの試験場で苗木を育てているところを見たので、果物としての研究は原産地でも行われていると考えています。 昭和の6ー7年にはアメリカから日本に入っています。日本でも暖かいところでは栽培可能ですが、本格的な栽培はない様です。 日本へは栽培の多いニュージランドから輸入してるともありますが、キウイの様には知られていません。どこの国でもまだマイナーな果物です。 フェイジョア色いろ  アルゼンチンで見たフェイジョアの花 アルゼンチンで見たフェイジョアの花 アルゼンチンで見たフェイジョアの藪 アルゼンチンで見たフェイジョアの藪

 KBが初めてフェイジョアの花を見たのはアルゼンチン中部の町です。乾燥した芝地の庭に植えられた高さ4~5mの藪になった木にきれいな赤い花がわずかに残っていました。 花は蕾の状態から花盛り、花弁が落ち長い雌蕊が残っている状態までが一度に見られました。  コロンビア由来のフェイジョアの花 コロンビア由来のフェイジョアの花

彼の奥さんが子供のころ食べたフェイジョアを食べたいと2000年にコロンビアの実家から持ってきた種をまいて育てた木です。8年もたつのに実が付かないということでした。 このフェイジョアは自家受粉では実がつかない種類かもしれません。 14年目に咲いた花は直径4cm位で雄蕊は2cm位でした。まだ実が付いた形跡はありません。 |