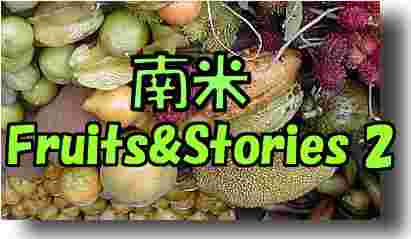
キャッサバ
 2020年2月22日、3月5日、3月17日修正
2020年2月22日、3月5日、3月17日修正日本名  キャッサバ、イモノキ キャッサバ、イモノキ中国名  木薯、树薯 木薯、树薯ブラジル名 ハイチ名  cassava、yuca cassava、yucaポルトガル名 スペイン名 英語名  cassava、 manioc、 mandioca cassava、 manioc、 mandiocaアフリカ名 マレイシア名 フィリピン名 タイ名  man samparang、mam mai man samparang、mam maiインドネシア名 インド名  tikhoor、maravalli、kuri aloo tikhoor、maravalli、kuri aloo Manihot esculenta Crantz Manihot esculenta Crantz新大陸のいも  キャッサバは中米から南米に由来する熱帯の数メートルになる草のような灌木です。葉柄は長く葉は深く切り込まれて3から9に分かれています。茎はあまり枝分かれしないで伸びます。
茎には葉の落ちた痕が残ってゴツゴツです。
キャッサバは中米から南米に由来する熱帯の数メートルになる草のような灌木です。葉柄は長く葉は深く切り込まれて3から9に分かれています。茎はあまり枝分かれしないで伸びます。
茎には葉の落ちた痕が残ってゴツゴツです。花は上の方が小さめの雄花で、下のふくらんだのが雌花の蕾ようですが写真ではわからないです。果実は長い果柄の先にぶら下がっていて、長さ2cm、太さ1.5cm位で6本の稜があります。 コロンブスが新大陸に来た時にはすでにカリブ海を囲む中央アメリカ北部、南米の北部、⻄インド諸島の各地で食料として栽培されていました。 キャッサバは植物体全体に有毒成分を含みますが、根にデンプンを貯めて食用になる芋ができます。栽培は茎を短く切って挿しておくだけで良いので簡単です。新大陸の熱帯では古くから各地で栽培されてきました。 キャッサバ芋は味のない白いサツマイモと言った感じで、食感はホクホク感もねっとり感もなく少し筋っぽいサツマイモ とジャガイモの中間と言ったとろでした。(自家菜園の小さな畑に植えてありました) 


原産地 各地で栽培されているキャッサバの原産地については中米(メキシコ南部からグアテマラ)とブラジル北西部ペルー寄りのアマゾンとする説もあります。キャッサバ属の植物は135種もあって原産地の可能性がある、種の多様性の高いところはメキシコとブラジルの北東部、中央部、南西部にあることがわかっています。 最近の研究で原産地はアマゾンの熱帯雨林の南にあるサバンナ、(ブラジルでいうセラード)の可能性が最も高いとされています。ブラジル南西部のボリビアやパラグアイに接する辺りはキャッサバの種の進化の中心地の一つで、この地域で8千年から1万年前にキャッサバの初期的栽培が始まったと推定されています。 多くの品種がありますが2つに分けます キャサバは厳密ではないですが、有毒成分が多いか少ないかによって、大きく2つの系統に分けられています。 キャサバに含まれる毒成分は青酸配糖体リナマリン(linamarin) とロタウストラリン( lotaustralin)で、リナマリンが主で、  芋には0.01から0.05%含まれています。配糖体は腸内で分解されると有毒なシアン化水素を生じます。
強い毒ですが、加熱、発酵、乾燥、水洗によって除くことができます。
毒の少ないキャッサバは苦味が少ないので甘カッサバと言います。アイピム(aipim)はツピー語で甘キャッサバを指します。
食用にするには毒の少ない甘味種が選ばれます。毒成分は芋の外皮に多く、中身には少ないので、皮と芯を除いて、煮て食べます。
芋には0.01から0.05%含まれています。配糖体は腸内で分解されると有毒なシアン化水素を生じます。
強い毒ですが、加熱、発酵、乾燥、水洗によって除くことができます。
毒の少ないキャッサバは苦味が少ないので甘カッサバと言います。アイピム(aipim)はツピー語で甘キャッサバを指します。
食用にするには毒の少ない甘味種が選ばれます。毒成分は芋の外皮に多く、中身には少ないので、皮と芯を除いて、煮て食べます。毒成分の多い種類は苦キャッサバです。苦味種のほうが甘味種よりもデンプン含量が多いとされています。食用には除毒します。工業原料の澱粉をとるために栽培するのに向いています。 学名のM.esculentaは苦いキャッサバのグループに入ります。 キャサバは生育期間が色々有り、早いものは、苗を植え付けてから8カ月で収穫できますが、20カ月もかかるものまであります。今は早生の品種が栽培されます。 栽培されているキャッサバの葉の形は色々ありますし、芋の中身の色も白色、黄色、少し赤いのもあります。 伝播  コロンブスが新大陸に来た時にはすでにカリブ海地方から南アメリカでは重要食料として栽培されていました。先住民がキャッサバの芋をすりつぶして水分を絞ってから薄く広げて焼き、パンを作っているのを見て、キャッサバは航海中の食料として役立つとして、すぐにポルトガルとスペインの航海者によりに取り入れられ、船乗りが行った熱帯の国々に広まりました。この際、彼らは植物だけでなく栽培、毒抜き、保存食作りの技術も同時に伝えています。16世紀初めに最初に持ちだされたキャッサバは甘味種だとされています。
コロンブスが新大陸に来た時にはすでにカリブ海地方から南アメリカでは重要食料として栽培されていました。先住民がキャッサバの芋をすりつぶして水分を絞ってから薄く広げて焼き、パンを作っているのを見て、キャッサバは航海中の食料として役立つとして、すぐにポルトガルとスペインの航海者によりに取り入れられ、船乗りが行った熱帯の国々に広まりました。この際、彼らは植物だけでなく栽培、毒抜き、保存食作りの技術も同時に伝えています。16世紀初めに最初に持ちだされたキャッサバは甘味種だとされています。アフリカへの伝播 16世紀末にはポルトガル人により西アフリカのナイジェリアやギニア湾岸の国に初めて持ち込まれています。17世紀に奴隷貿易が盛んになると、ブラジルを支配していたポルトガル人は奴隷の航海中の食料用に、栽培が容易なキャッサバをアフリカ各地に広めました。 東アフリカに伝わったのは遅くて1736年にブラジルからレユニオン(Réunion)に導入したのが始まりで、ザンジバルには1799年に導入されています。 20世紀になってアフリカではバッタの食害による飢饉に備えるために奨励されたので、栽培は急速に広がりました。 今では、熱帯アフリカではキャッサバを主食とする国もあり重要食料資源です。アフリカは全世界のキャッサバ生産の半分くらいを生産し消費ています。 ナイジェリア、コンゴ、ガーナ、アンゴラは生産の多い国です。 アジアへの伝播  1571年にスペイン人がフィリピンを占領したときメキシコからフィリピンへ持ってきたのが始まりです。フィリピンから中国を経てジャワに伝わり、インドネシアからマレイシア、ビルマへと伝わっています。インドへは1794年に試験作物として入っています。
1571年にスペイン人がフィリピンを占領したときメキシコからフィリピンへ持ってきたのが始まりです。フィリピンから中国を経てジャワに伝わり、インドネシアからマレイシア、ビルマへと伝わっています。インドへは1794年に試験作物として入っています。アジアでは食料としての重要度は低く、1850年代になって澱粉の需要が高まったのに伴って澱粉原料として多く生産されるようになり、 現在は工業原料としての澱粉を生産しています。アジアは全世界の生産量の約25%を生産していてタイ、インドネシア、ベトナムが主要生産国です。 世界的に生産の多い国はナイジェリア、コンゴ、タイ、ブラジル、インドネシア、ガーナですが、アフリカとブラジルは食用に自家消費が多くて世界の貿易市場に出てくるのはアジア産のキャッサバ製品です。 食べる キャッサバは植えて置けば必用な時に芋を掘って食べれば良いですが、掘った芋は保存が効かないので、ファリーニヤという乾燥した保存食にします。キャッサバ食には毒抜きと保存食作りの技術が必用です。  KBはお昼に、茹でたキャッサバ芋、時には茹でてから短冊に切って揚げたキャッサバスティックをよく食べました。 昔からの保存食としては芋を磨り潰して、水分を絞り取って、芋を加熱乾燥して粉状にしたファリーニヤ(farinha)があります。 この磨り潰した芋の絞り汁を静置すると澱粉が取れるので、澱粉は良く水洗いして食用にします。上澄み液は発酵してツクピー(tucupi)という酸味調味料を作ります。 今でもファリーニヤ作りは先住民の手仕事のやり方も残っていますが、たいていは作業場で機械で磨り潰したり圧縮機で絞って作っています。 キャツサバを磨り潰して、水と混ぜて篩にかけてから、貯めて置き沈んだ澱粉から作った粉がキャッサバ澱粉、タピオカ(tapioca )です。 ファリーニヤは色々な料理に振りかけて食べましたが、KB には味の印象はありません。ツクピーはトウガラシや香草を入れたのも売っています。  キャッサバを芋として食べるときは茹でて、汁を流しますから毒の心配はありません。茹でた芋をステイックに切って油で揚げたのはさらに毒は少なくなるというわけです。
キャッサバを芋として食べるときは茹でて、汁を流しますから毒の心配はありません。茹でた芋をステイックに切って油で揚げたのはさらに毒は少なくなるというわけです。KBはキャッサバの焼きいもは見なかったです。 ボーロ(bolo)もありました、ファリーニャにココナツと砂糖を加えて小さく丸めて焼いたボーロの径は1.5cm程で、口に入れるとすぐに崩れてココナツの香りと甘さがあった。  ポンデケージョ(pão de queijo)はキャッサバ澱粉とチーズを混ぜて無発酵で作るパンです。これはモチモチした食感でチーズの匂いのする白っぽい小さい丸いパンです。 ポンデケージョを作るにはポルヴィーリョ(polvilho azedo)と言って、発酵した芋を磨り潰して作る少し酸っぱい澱粉を使うのが本場の味とのことです。ドライブインでよく見ました。パラグアイではチパと言っていました。
ポンデケージョ(pão de queijo)はキャッサバ澱粉とチーズを混ぜて無発酵で作るパンです。これはモチモチした食感でチーズの匂いのする白っぽい小さい丸いパンです。 ポンデケージョを作るにはポルヴィーリョ(polvilho azedo)と言って、発酵した芋を磨り潰して作る少し酸っぱい澱粉を使うのが本場の味とのことです。ドライブインでよく見ました。パラグアイではチパと言っていました。パモーニア(pamonha )はキャッサバ澱粉とココナツミルクとココナツの白いところ(胚乳)を細かくしたものを混ぜてバナナの葉に包んで蒸したお菓子です。ココナツ風味の少し甘い粽というか外郎のような感じです。 カサベ(casabe)キャッサバのカサベ(スペイン語はcasabe de yuca)は、湿っているキャッサバ粉を鉄板の上に広げて焼いた薄いパンです。サクットした煎餅ですが焼き加減で硬いのも軟らかのもあるようです。  アフリカの食べ物 アフリカでも水につける、発酵する、磨り潰して乾燥する、加熱するといった毒抜きはブラジルと同様にやっています。
アフリカの食べ物 アフリカでも水につける、発酵する、磨り潰して乾燥する、加熱するといった毒抜きはブラジルと同様にやっています。食べ方は茹でて食べることはもちろんあると思いますが、水分の多い粉食系の料理がよく紹介されています。 KBは不勉強につき、アフリカにもパンのような乾いた食べ物があるかどうかは知りません。 ガリ(gali)というブラジルのファリーニアに相当するキャッサバの加工品があります。これに湯を加えて練って団子か粥状にして主食にしています。 フフ(fufu)はキャッサバ芋を茹でてもちのように搗いた料理で、主食とされています。 キャッサバの若葉は野菜として茹でてから良くつぶして食べます。 KBはブラジルで葉を野菜として食べるかどうかは知りません。 日本 日本ではキャッサバ澱粉は表に出ないところで色々な食品に使われています。見てわかるのはタピオカドリンクです。これはキャッサバ澱粉を球状にして乾燥したタピオカを茹でて澱粉の粒を糊にした物です。 KBが試したところ黒いつぶのタピオカミルクティーのプヨプヨしていて、口内ですぐには溶けない食感には違和感があります。白いつぶのタピオカココナツミルクの方が本当のタピオカらしかった。  マンジョカとろけるほどに崩れ煮え ジャバクワラ歌会 中島昌枝 マンジョカとろけるほどに崩れ煮え ジャバクワラ歌会 中島昌枝 マンジョカのひと抱へほど商える サンパウロ 山本英峯子 マンジョカのひと抱へほど商える サンパウロ 山本英峯子 木藷掘る子等にも分けて隣にも サンパウロ 亀山キヨミ 木藷掘る子等にも分けて隣にも サンパウロ 亀山キヨミ名前色々 ブラジルには現地名がいくつもあり、現在の言葉に入っています。 ツピ族の言葉に由来するマニオカ(manioca)、マニオク(manioc)、マンジオカ(mandioca)、マンジオ(mandio)、マニホット(manihot)、マニバ(maniva)はポルトガル語やスペイン語のマンジオカ(mandioca)になっています。 キャッサバ(cassava)はハイチの現地名で、タイノ族の言葉カサビ( caçabi、casávi、 cazábbi)に由来してフランス語に入っています。 ユッカ(yuca)もハイチのタイノ族の呼び名に由来しスペイン語に入っています。 キャッサバ芋から作った澱粉の呼び名 tapiocaはツピー語で”搾った粕”という意味ですからファリーニアというか粗製の澱粉と言ったところです。ポルトガル語で今の普通の澱粉はamidoです。 日本語と中国語の「木薯」はマレー語「ubi kayu」、タミル語の「mara valle kilangu」は「いもの木」あるいは「木のいも」の意味で、発想は共通しています。 キャッサバはアフリカ、インドネシア、インドでは民族、言語、地域によって多くの名前で呼ばれています。 キャッサバの持ち込まれた国の呼び名には、どの国の人が持ってきたか、どこから伝わってきたかを示すようなのもあります。 キャッサバ続きはここ |